2025/3/18 (Tue)
高志の紅ガニで大満足の後に向かったのは、世界遺産(文化遺産)合掌の里「五箇(ごか)山」
高速を降り積雪の多い中、Naviを頼りに向かった先で、「車両通り抜けできません」が二つに折れ「車両進入禁止」を隠してしまっており、気付かずに進入して何とか戻ってこれた
冬季の豪雪地帯とはいえ、世界遺産なのだから、表示はしっかり!多言語で!!
菅沼集落は、1970年に国の史跡指定を受け、1994年に重要伝統的建造物群保存地区に選定された
人の住む合掌造りの家屋と、その周辺の景観は、伝統的集落の価値が高く、1995年12月に、五箇山の相倉合掌造り集落、岐阜県白川村荻町合掌造り集落とともに、世界文化遺産に登録された
5つの谷間(赤尾谷・上梨谷・下梨谷・小谷・利賀谷)から構成された集落群の総称「五箇山」と呼び、加賀藩政時代には約70の集落があった2004年に砺波地方南部平野部の、福野町・福光町・井波町・城端町・井口村そして山間部の平村・上平村・利賀村の4町4村が合併し、南砺市となった
天に向かってお念仏の手を合わせるような合掌屋根が、五箇山の暮らしを守ってきた
現存する合掌造り家屋は、江戸時代中期からと推測され、約100年~200年前のものが多く、古いものは400年前という
屋根の勾配は45度~60度あり、断面は正三角形に近く、雪が滑り落ちやすい形
大きな屋根を支えるのは、根元の曲がったチョンナと呼ばれる太い梁で、山の斜面に生育した自然に曲がったナラの木を用いている
合掌の組み立てには釘は一切打たず、稲縄とネソと呼ばれるマンサクの木を使った
山形に組み合わされた屋根の下地となる「合掌」(叉首(さす))の下端は細くとがっていて、桁の上に渡された叉首台「ウスバリ」の両端にあけられた窪みに差してあるだけで、地震や雪による屋根の重みにも柔軟に対応する仕組みになっている
五箇山民俗館は、4時閉館の直後で入れず
神明社の鳥居までは、除雪がされず入れず
塩硝 (えんしょう)の館は、冬季休業?
五箇山民俗館は、4時閉館の直後で入れず
神明社の鳥居までは、除雪がされず入れず
塩硝 (えんしょう)の館は、冬季休業?
塩硝とは硝石(しょうせき)で、硫黄と炭素と混ぜて、黒色火薬(鉄砲火薬)の原料となる硝酸カリウム(KNO3)のことで、加賀藩では五箇山で生産された塩硝が、重要な換金生産物だった
一階の天井は簀子(すのこ)張りになっており、いろりからのぼる熱気を通過させて、蚕室を暖める働きがあった
一階の天井は簀子(すのこ)張りになっており、いろりからのぼる熱気を通過させて、蚕室を暖める働きがあった
いろりからの煙が虫除けとなり、木材や茅葺屋根を長持ちさせた
二階は、広い作業空間と採光、保温を求められた養蚕に使用され、一階は、紙漉き場と住居として使われ、床下では、土や蚕の糞、山草などを混ぜて発酵させ、硝酸塩を生成していた
二階は、広い作業空間と採光、保温を求められた養蚕に使用され、一階は、紙漉き場と住居として使われ、床下では、土や蚕の糞、山草などを混ぜて発酵させ、硝酸塩を生成していた
甘酒をいただきに、与八にあがり込む
宿泊もできるようだが、江戸時代の暮らしを実感できそうだ
日が暮れる前に、五箇山を後にする
つけ麺は、めっちゃ多い
お店の名物「ガッツリ!ラーメン」は、濃い味家系
富山市中心部で富山大空襲の復興事業に従事していた、肉体労働者のための塩分補給として、醤油を濃くしたラーメンを作ったのがきっかけで「富山ブラック」が生まれたと言われる
宿泊もできるようだが、江戸時代の暮らしを実感できそうだ
日が暮れる前に、五箇山を後にする
五箇山の合掌造り集落が、もう一つあったのは知らなかった、残念
白川郷へも行く予定だったが、明日は雨雪予報のため、五箇山だけを今日に繰り上げて訪問した
先ずはしっかり肉の入った、餃子朝から氷見イワシ、高志の紅ガニと名物にありついたので、富山湾寿司を明日に回し、今晩は「ガッツリ!えびすこ」で、富山ブラック・黒ラーメン
つけ麺は、めっちゃ多い
お店の名物「ガッツリ!ラーメン」は、濃い味家系
富山市中心部で富山大空襲の復興事業に従事していた、肉体労働者のための塩分補給として、醤油を濃くしたラーメンを作ったのがきっかけで「富山ブラック」が生まれたと言われる
お土産を買いに回る予定

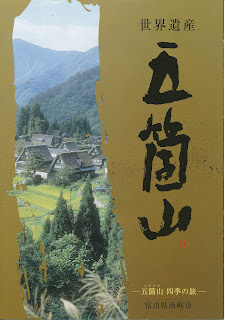





























0 件のコメント:
コメントを投稿