2022/11/24
那珂川町の宝蔵院は、「那須三十三観音」24番札所
文亀2年(1502)甚誉上人によって創建された。その後明治12年に火災によって堂宇は消失し、灰燼に帰したが、明治28年に再建された。
その後昭和期に入って、堂宇の修繕、改築が行われ現在に至る。
札所本尊の如意輪観世音菩薩は、本尊阿弥陀如来の右の脇侍に鎮座をしている。
何の実なのか不明
東に1kmほどの光照寺は、関東八十八ヵ所霊場、ぼけ封じ関東三十三観音、那須三十三所観音、八溝七福神の札所
道端の公孫樹(イチョウ)が光り輝いています
八溝七福神は弁財天
那須三十三所観音は千手観音
ぼけ封じ関東三十三観音は、阿摩提観音(あまだいかんのん)
関東八十八ヵ所霊場の本尊は阿弥陀如来
那須記に貞信が神田城構築のとき、増倉比丘を招聘して一寺を建立し、鬼門守護とした際に記念に植えられたという、町指定文化財「公孫樹」
樹高20m、推定樹齢450年
さてお昼は、那珂川町なす風土記の丘にある「そば処 ふれあいの舎」もりそばにプラス100円で、かき揚げが二枚付きます
蕎麦は手打ち感満載で、腰のある麺で、甘めのつゆと良く合っています
今までの中でも、かなり高得点の蕎麦でした
隣には江戸時代の民家が二棟、民族資料館がありました
民家の反対側には、ザゼンソウの自生地があるようです
お次は那須三十三所観音22番札所の「霊牛山威徳院 極楽寺」
栴檀(センダン)の実
同時に栃木十三仏霊場第13札所、八溝七福神、八溝山麓十宝霊場でもあります
ようやくと今日の目的地である、芦野(あしの)に入りました
武家屋敷前のしだれ桜は、電線が邪魔ですね
揚源寺(ようげんじ)のメタセコイアの紅葉
アスナロウはヒノキ科の常緑高木で寒冷地の樹木であるが、このアスナロウは分布上南限に近く、平地に近い所でこれほどの巨木は珍しいという。当地方のアスナロウは最大の巨木である。
不動明神の御神木のためか、神剣が立てられている
揚厳寺は、江戸時代初期の寛永年間(1624~1644)に栄賢(えいけん)和尚が中興(ちゅうこう)開山し、芦野集落センター裏の愛宕山(あたごやま)から現在地に移転したと伝えられている。大正時代の初期、芳賀郡の延生(のぶ)の地蔵尊の分霊を移した。
那須歴史探訪館も、隈研吾氏の設計だそう
芦野城とも、御殿山とも、桜ヶ城とも称される
江戸時代には交代寄合旗本芦野氏の陣屋があった所だそうだ
とりあえず頂上を目指す
那須連峰が雲に隠れている
築城の年代には二説あり、一つは天文年間(1532~55)芦野資興の代であり、もう一つは天正18年(1590)芦野盛泰の代とも言われているが明らかではない。
いわゆる本丸にある樅ノ木は、電波塔との共演
サクラの名所として有名だそうだ
二の丸には居城があり、御殿や蔵、表門と裏門があった。御殿は、木羽葺で間口約29㍍、奥行き約11㍍あり、玄関、客間、奥の間、大広間、宿直間、中間部屋、広敷台等に区切られ、建物の奥には陰殿(トイレ)もあったそうだ
那須町のこうやまき
芦野御殿山を降りて、旧奥州街道は、現在の「関東ふれあいの道」
那須三十三所観音第8番札所の、三光寺は、日本三所聖天(浅草、妻沼、芦野)のひとつだそうです
那須三十三所観音第7番札所および下野西国三十三所観音第5番札所の、最勝院
芦野氏陣屋裏門は、明治の初期に競売により民間に払い下げられ、今では民家の門となっている
芦野氏第三の城、御殿山の北側にあった陣屋の裏門を移設したものです
正面の岸壁の上に、館山城があったようだ
道と川百選「柳街道(芦野バイパス)」
石の美術館ストーンプラザ
奥州街道道標
だったら全国旅行支援で泊まっちゃおうかという流れで、12月の宿を予約
風格のある、温泉入り口
温泉報告は、12月の宿泊時に
芦野へ向かう途中で気になった「堂の下の岩観音」
日陰になってしまい、写真に撮るのが難しい

























































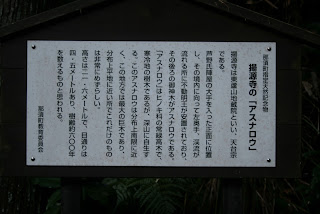
















































































0 件のコメント:
コメントを投稿